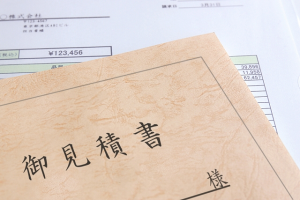住まいのリフォームが終わったご家族や友人に、どんなお祝いを贈ればよいのか迷ったことはありませんか?
「リフォームのお祝いに何がいいですか?」という疑問は、リフォームを経験した相手が身近にいる方なら一度は感じるものです。
この記事では、リフォームのお祝いを渡すタイミングや、どんなプレゼントがふさわしいかといった基本から、相場の目安、表書きの書き方、のし袋の選び方まで丁寧に解説します。
また、「ご祝儀は必要なのか?」「花やお菓子は贈ってもよいのか?」といった、よくある悩みにもお答えします。
親に贈る場合や、ビジネス関係のお祝いとして渡すケースなど、関係性ごとのポイントも押さえているので安心です。
さらに、リフォームお祝い金を渡すときのマナーや、改築祝いプレゼントとして人気のアイテム、もらった側のお返しの考え方や添えるメッセージ例まで網羅しています。
「何を贈れば失礼にならないのか」「気持ちをしっかり伝えるにはどうすればいいか」そんな不安を解消できるよう、実用的でわかりやすくまとめました。
リフォームのお祝いを通じて、気持ちのこもった関係づくりができるよう、ぜひ参考にしてください。
- リフォームのお祝いにふさわしい贈り物の選び方がわかる
- ご祝儀やお祝い金を渡すべきかの判断基準がわかる
- 表書きや水引、袋の正しい使い方がわかる
- お祝いを贈る相手や関係性ごとのマナーがわかる
リフォームのお祝いで失敗しない基本マナー
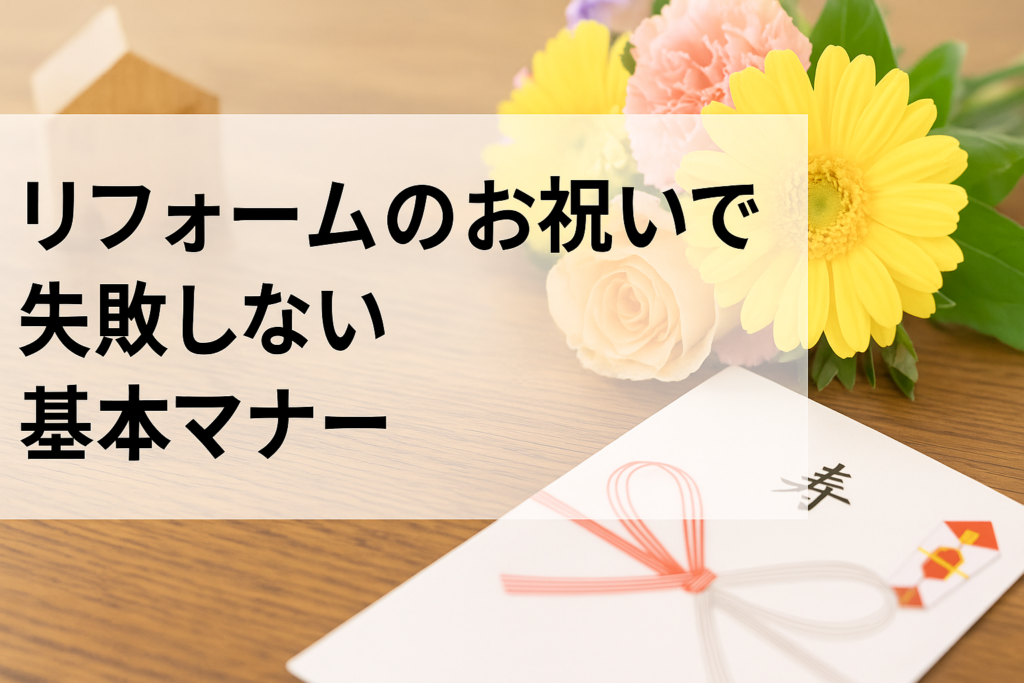
リフォームのお祝いは何を贈るのが正解?
リフォームのお祝いには、現金や商品券、実用的な日用品、花束などがよく選ばれます。ただし、相手の好みやライフスタイルによって適した贈り物は変わるため、万人にとっての「正解」は存在しません。
それでも、「相手が気を遣わず、実際に役立つもの」を贈ることが、喜ばれるプレゼントの基本です。
まず、現金や商品券は非常に実用的で、どんな相手にも対応できる定番の贈り物です。特に相手の趣味や生活スタイルがわからない場合は、好みを外す心配がなく、自由に使ってもらえることがメリットです。
ただし、現金をそのまま渡すことに抵抗がある場合には、商品券やカタログギフトにすることで少しカジュアルさを加えることができます。
一方、日用品や家電といった実用品も人気があります。例えば、タオルセットやキッチン用品は新しい空間での生活にすぐ役立ちますし、空気清浄機や加湿器などの小型家電も新しい環境を快適にするアイテムとして重宝されます。
ただし、すでに同じようなものを持っている場合もあるため、事前に相手の持ち物や希望をそれとなく聞いておくのが安心です。
花束や観葉植物もよく選ばれる贈り物ですが、注意点もあります。赤い花や火を連想させる植物は、火事などの災厄を連想させるため避けた方がよいとされています。
長持ちするプリザーブドフラワーや、縁起の良い観葉植物などを選ぶと、インテリア性もありおすすめです。
このように、リフォームのお祝いには多くの選択肢がありますが、「相手が本当に喜ぶか」を基準に選ぶことが最も大切です。形式ばらず、心のこもったプレゼントを選ぶことが、何よりのお祝いになります。
ご祝儀は必要?リフォームの工事とお金のマナー
リフォームに際してご祝儀を渡すかどうかは、リフォームの規模や相手との関係性によって判断するのが一般的です。
新築のように明確な慣習があるわけではありませんが、大規模な改築やフルリノベーションを行った際には、ご祝儀や贈り物を渡すのがマナーとして定着しつつあります。
特に、親族や親しい友人、会社関係者がリフォームをした場合は、「おめでとう」の気持ちを込めて、何らかの形でお祝いを贈るのが望ましいとされています。
とはいえ、すべてのリフォームにご祝儀が必要というわけではありません。たとえば、トイレやキッチンの一部だけを交換するような小規模なリフォームであれば、改めてご祝儀を用意する必要はないと考えられています。
また、ご祝儀として現金を包む場合には、結婚式や新築祝いと同じく、偶数ではなく奇数(1万円・3万円など)の金額が縁起が良いとされています。
お金を包む際には、紅白の蝶結びの水引が付いた祝儀袋を使用し、表書きには「御祝」や「改築御祝」と記載します。相手が目上の場合やビジネス関係者である場合には、特にマナーに配慮しましょう。
なお、現金ではなく商品券やギフトカードを選ぶ場合でも、のし紙を付けて丁寧に包むのがマナーです。品物の場合も同様に、包装や表書きをきちんと整えることで、気持ちがより伝わりやすくなります。
リフォームのお祝いでご祝儀が必要かどうか迷ったときは、相手のリフォーム内容を確認し、周囲の親族や関係者とも相談するのがよい方法です。地域の習慣や家庭ごとの考え方によっても違いがあるため、柔軟な対応が求められます。
リフォームのお祝いの金額は?相場はいくらぐらい?
リフォームのお祝いの金額は、贈る相手との関係性やリフォームの規模によって異なります。
目安としては、家族や親戚などの親しい間柄であれば1万円から3万円、友人や知人には5,000円から1万円、上司や取引先には5,000円程度が妥当とされています。
特に注意したいのは、相場よりもあまりに高額な金額を渡すと、かえって相手に気を遣わせてしまう点です。お祝いのつもりがプレッシャーになってしまっては、本末転倒です。反対に、金額が相場から大きく外れて少なすぎる場合も、失礼にあたる可能性があります。
また、兄弟姉妹間や親子間でお祝いをする場合には、単なる「お祝い」というよりは「家計の助け」や「親孝行」としてまとまった金額を贈ることもあります。
この場合は、形式にこだわりすぎず、柔軟に対応しても問題ありません。ただし、他の家族や親族と贈るタイミングが重なるようであれば、あらかじめ金額や内容について話し合っておくと、トラブルを防げます。
一方で、会社関係や取引先などビジネス上のお付き合いでは、あまり高額なお祝いを贈ると不自然になることもあります。業務上の関係性を考慮し、控えめな金額で失礼のないように整えることが大切です。
ちなみに、現金を渡す際には、縁起を担いで「奇数」の金額にするのが通例です。これは「割り切れない=縁が切れない」とされるためで、1万円や3万円などが特に好まれます。
このように、お祝いの金額は一律ではなく、相手の立場や状況、リフォームの規模などを考慮して決める必要があります。無理のない範囲で、相手の喜びに寄り添う金額設定がベストと言えるでしょう。
表書きの書き方や水引の選び方とは
リフォーム祝いで現金や品物を贈る際には、表書きや水引のマナーにも注意を払う必要があります。これらは単なる装飾ではなく、贈り物に込める気持ちを丁寧に伝えるための大切な要素です。
間違った形式で贈ると、気持ちが正しく伝わらなかったり、非常識と受け取られてしまう可能性もあるため、しっかり確認しておくと安心です。
まず表書きについてですが、リフォーム祝いの表書きには「御祝」「御礼」「祝御改築」「改築御祝」といった言葉を使います。
一般的には「御祝」で問題ありませんが、リフォームが大規模で家全体の構造を変更しているような場合は、「改築御祝」などより具体的な表現を使うと、相手に誠意が伝わります。
小規模なリフォームの場合には「改装御祝」という表記も選択肢に入りますが、あくまで工事の内容に応じて選ぶのがポイントです。
次に、水引の種類についてです。水引には「蝶結び(花結び)」と「結び切り」の2種類があります。リフォーム祝いでは、何度あっても喜ばしいこととされるため、紅白の蝶結びを選ぶのが一般的です。
これは新築祝いなどと同様で、「何度でも繰り返してよい慶事」に使われる水引の形式です。逆に「結び切り」は一度きりで終えるべきお祝い、たとえば結婚祝いや快気祝いなどに用いられますので、リフォーム祝いには不向きです。
表書きと水引が整ったら、名前の書き方にも注意しましょう。個人で贈る場合はフルネームを楷書で書くのが基本です。夫婦連名で贈る場合は、右側に夫の名前、左側に妻の名前を並べて書きます。
また、会社名義で贈る場合には、会社名と代表者の名前をセットで記載します。
見た目の美しさにも気を配りたいところです。表書きの文字がかすれていたり、斜めになっていると、どれだけ立派な贈り物をしても印象が悪くなってしまいます。筆ペンや濃いインクのサインペンを使い、丁寧に仕上げることが大切です。
正しい表書きと水引の選び方を守ることで、形式を重んじる場面でも安心してお祝いを渡すことができます。気持ちを形にする最後の仕上げとして、ぜひ丁寧に準備してみてください。
親にリフォーム祝いを贈るときのポイント
親にリフォーム祝いを贈る場合は、通常のマナーを守るだけでなく、家族ならではの心遣いが求められます。形式よりも気持ちが重視される関係性ですが、それでも基本的な礼儀を守ることで、贈る側の誠意がより深く伝わります。
まず前提として、リフォームの内容をよく理解しておくことが大切です。たとえば、老朽化した設備を修繕するためのリフォームと、快適さを求めた趣味的なリノベーションでは、親が受け取る印象も異なります。
家族とはいえ、リフォームが親にとって「前向きなできごと」かどうかを見極めることが、お祝いを渡すべきかを考える第一歩です。
金額については、一般的な相場よりも柔軟に考えて問題ありません。相場では1万〜3万円が目安とされていますが、親孝行や感謝の気持ちを込めて、それ以上の金額を包むこともあります。
このとき、あくまでお祝いとして贈るのか、援助の意味を込めるのかによって伝え方を変えるとよいでしょう。もし援助に近い意味で渡す場合には、「手伝いたい気持ちから」と前置きすることで、負担に感じさせずに受け取ってもらいやすくなります。
品物を贈る場合は、実用的でかつ気持ちのこもったアイテムを選ぶのが理想です。たとえば、新しいリビングに似合うクッションや、おしゃれな電気ポットなど、日常使いしやすいものがおすすめです。
親の趣味や好みを理解しているからこそできる選び方をすると、より喜んでもらえるでしょう。ただし、インテリアなど好みが分かれるものについては、サプライズではなく事前に好みを聞いておく方が無難です。
贈り方についてもポイントがあります。手渡しで直接言葉を添えて渡すのがベストですが、遠方に住んでいるなどの事情がある場合は、郵送でも問題ありません。
その場合はメッセージカードを添え、「リフォームお疲れさまでした」「これからも快適に過ごしてくださいね」といった一言を加えると、ぐっと温かみが増します。
親へのお祝いは、金額や品物そのものよりも、「気にかけているよ」「応援しているよ」という気持ちが伝わるかどうかが最も重要です。形式にとらわれすぎず、心を込めたやりとりを意識すると、親子の絆がさらに深まる機会となるでしょう。
リフォームのお祝いに喜ばれる贈り物と注意点

改築祝いプレゼントのおすすめアイデア
改築祝いのプレゼントを選ぶ際は、相手のライフスタイルや家の雰囲気に合わせた実用的かつ気の利いた品物を選ぶことが大切です。ただ高価なものを贈るのではなく、「もらって嬉しい」と感じてもらえることを意識しましょう。
まず定番として人気が高いのが「カタログギフト」です。これは相手自身が好きな商品を自由に選べるため、好みを外す心配がありません。
特にリフォーム直後は、必要な物が多かったりインテリアの雰囲気に合うものを探していたりする時期でもあります。カタログギフトは価格帯も選べるため、贈る側にとっても柔軟に対応しやすい選択肢です。
また、家電製品も改築祝いとして重宝されます。たとえば、デザイン性のある電気ケトルやトースター、空気清浄機などは、実用性と見た目の両面で喜ばれることが多いです。
ただし、すでに持っている可能性があるため、事前にそれとなく確認しておくことが重要です。サイズが大きすぎたり置き場所に困るような品は避け、使いやすいコンパクトなタイプを選ぶとよいでしょう。
インテリア雑貨を選ぶ場合には注意が必要です。贈る側としてはおしゃれなアイテムを選びたくなりますが、インテリアには個人の好みが強く出るため、ミスマッチが起きやすい分野でもあります。
どうしても贈りたい場合は、相手の好みが明確にわかっているときに限るか、無難でシンプルなデザインのものを選ぶようにしましょう。
他には、消耗品である「高品質な日用品」も人気です。タオルセットや食器用洗剤、バスソルトなど、普段より少し贅沢なアイテムを選ぶと、お祝いらしさが演出できます。
特に複数あっても困らないものは、他の人と贈り物がかぶっても気にならない点が魅力です。
このように改築祝いのプレゼントには多くの選択肢がありますが、どれを選ぶにしても「相手が喜んでくれるかどうか」を最優先に考えることが大切です。
品物の内容とともに、贈る側の気持ちも丁寧に伝えることが、心に残るお祝いにつながります。
リフォームお祝い金を渡すときのマナー
リフォームのお祝い金を渡す際には、金額だけでなく、タイミングや渡し方、包み方といったマナーにも気を配る必要があります。お祝いの気持ちが伝わるよう、形式的な部分も丁寧に準備しておきたいところです。
まず渡すタイミングですが、基本的には「リフォーム完成の報告を受けてから1週間以内」が望ましいとされています。これは、新たな生活が始まったばかりの時期にお祝いを贈ることで、気持ちも盛り上がっており、より喜ばれやすいからです。
もし都合で直接会えない場合には、郵送でも問題ありませんが、その場合はメッセージカードなどを添えて気持ちを伝える工夫をしましょう。
金額については、贈る相手との関係性に応じて変えるのが基本です。たとえば、家族や親戚であれば1万円~3万円、友人や上司などの場合は5,000円~1万円程度が相場です。
また、お祝い金は偶数ではなく「1万円」「3万円」といった奇数の金額が好まれます。これは「割り切れない=縁が切れない」という意味を持ち、縁起が良いとされているためです。
お金を包む際には、ご祝儀袋を使うのがマナーです。リフォーム祝いにふさわしいのは、紅白の蝶結びの水引がついたご祝儀袋です。
表書きには「御祝」または「改築御祝」と書くのが一般的で、名前はフルネームで記載します。筆記具は黒インクか筆ペンを使い、丁寧に書くことを心がけましょう。
一方、注意したいのは、お祝い金を渡すことがかえって相手の負担になってしまう場合です。例えば、相手との関係がまだ浅かったり、相手が贈り物を遠慮するタイプだったりするケースでは、無理にお祝い金を渡さず、品物や手土産に留めるという判断も必要です。
このように、お祝い金は「気持ちを形にするもの」ではありますが、その渡し方ひとつで印象が大きく変わります。形式ばかりにとらわれず、相手に負担をかけない配慮も大切にしたいところです。
贈り物にふさわしい袋やラッピングとは
リフォーム祝いの贈り物は、中身だけでなく「見た目」も印象を左右する重要なポイントです。特に丁寧なラッピングや適切な袋に包まれていると、それだけで気持ちのこもった贈り物だと受け取られやすくなります。
ここでは、贈り物にふさわしい袋やラッピングについて解説します。
まず基本となるのは「のし紙」と「水引」です。現金や商品券を贈る場合はご祝儀袋を使用し、品物を贈る場合はのし紙をつけて包装します。
のし紙の表書きには「御祝」「改築御祝」などと書き、紅白の蝶結びの水引を選ぶのが一般的です。蝶結びは「何度あっても嬉しい祝いごと」に使うため、リフォーム祝いにふさわしい形式です。
包装紙については、落ち着いた色合いで上品なデザインのものを選ぶと安心です。カラフルすぎるものや奇抜なデザインは、お祝いの趣旨にそぐわない場合もあるため注意が必要です。
特に、赤色がメインの包装は「火」を連想させるため、リフォーム祝いでは避けたほうがよいとされています。
手渡しの場合には、紙袋に入れて持参するとスマートです。このときも、ブランド名が大きく入ったものや再利用の袋ではなく、できる限り清潔感のある無地またはシンプルなデザインの袋を使用しましょう。
袋にも一工夫を加えることで、全体の印象がぐっと良くなります。
郵送で贈る場合は、破損や包装の乱れを防ぐために、外装にも配慮しましょう。のし紙を「内のし」として品物に直接巻き、その上から緩衝材を入れた箱に梱包することで、見た目を保ったまま相手に届きやすくなります。
さらに、メッセージカードを同封する場合は、ラッピングの中に一緒に添えるか、外側に軽く貼っておくとよいでしょう。手書きでひと言添えれば、贈り物に温かみが加わります。
このように、袋やラッピングは単なる包装ではなく、「あなたの気遣い」を伝える重要な要素です。中身以上に相手の心に残るのは、こうした細やかな気配りであることも少なくありません。
花を贈るときに気をつけたいこと
リフォーム祝いに花を贈ることは、華やかで喜ばれる贈り物の一つですが、贈る際にはいくつかの注意点があります。見た目が美しいからといって安易に選んでしまうと、相手に不快感を与えてしまう可能性もあるため、マナーをしっかり理解しておきましょう。
まず、花の「色」には注意が必要です。赤色の花は一見すると華やかですが、「火」や「燃える」といったイメージに繋がるため、火災を連想させてしまうことがあります。
特にリフォームや改築など、新しい生活の門出においては、縁起の悪い印象を避けたいものです。そのため、白や淡いピンク、グリーン系など、柔らかく落ち着いた色味を選ぶと無難です。
また、花の「種類」にも気配りが必要です。例えば、菊は仏花として使用されることが多く、祝いの席には不向きとされています。棘のあるバラも、「刺す」「痛い」というイメージがあるため避けたほうがよいとされています。代わりに、胡蝶蘭やユリ、ガーベラなど、明るく上品な花を選ぶと好印象です。
次に、「形態」に関する配慮も重要です。花束は見た目が華やかで人気ですが、水換えや花瓶の用意が必要なため、贈る相手の手間になることもあります。
その点、プリザーブドフラワーやアレンジメントフラワーであれば、水やり不要で長期間楽しめるため、忙しい方や高齢者にも向いています。住まいのスペースを考慮し、小さめサイズのものを選ぶこともポイントです。
さらに、渡す「タイミング」にも気をつけましょう。リフォームの完成直後、つまり新しい生活が始まった直後に贈ることで、家の中がまだ整っていない状態を避け、スムーズに飾ってもらえる可能性が高まります。
配送する場合は、相手の在宅状況を確認しておくと安心です。
このように、花を贈る際は見た目だけで判断せず、色や種類、サイズ、タイミングにまで気を配ることで、心遣いの感じられる贈り物になります。相手の新生活を心から祝う気持ちが、花とともに伝わるような配慮を忘れないようにしたいものです。
心のこもったメッセージの書き方と例文
リフォーム祝いの贈り物に添えるメッセージは、形式的なものでも構いませんが、一言でも自分の言葉を加えることで、受け取る側の印象が大きく変わります。
文面には明確な決まりはありませんが、気をつけたいポイントや避けるべき表現がありますので、それらを押さえたうえで、心のこもったメッセージを作成することが大切です。
まず意識したいのが、「お祝いの言葉」「贈り物に関するひとこと」「締めの言葉」の三つの構成です。簡潔でありながら、温かさや気配りを感じさせる文章が理想的です。
たとえば、初めに「このたびはご改築おめでとうございます」と伝え、次に「ささやかではございますが、お祝いの品をお贈りいたします」、そして最後に「ご家族皆さまのますますのご多幸をお祈り申し上げます」と結ぶことで、丁寧な印象のメッセージになります。
避けるべき表現としては、「火」や「倒れる」などの忌み言葉が挙げられます。リフォームに関連するお祝いでは、火事や建物の損壊を連想させる言葉を使わないよう注意が必要です。
また、「終わる」「壊す」「燃える」「流れる」なども避けた方が無難です。無意識のうちに使ってしまうこともあるため、文面を完成させた後に一度見直すと安心です。
メッセージを書く際は、なるべく手書きにすると、より気持ちが伝わりやすくなります。字に自信がない場合でも、丁寧に書かれていることで、相手はあなたの真心を感じ取ってくれるでしょう。筆記具は、黒や濃紺などはっきりしたインクを使用し、薄墨などは避けるようにします。
以下に例文をいくつかご紹介します。
【友人向け】 「このたびはご改築おめでとう!新しい住まいでの毎日が、より快適で素敵なものになりますように。お祝いの気持ちを込めて、ささやかな品を贈ります。」
【上司や取引先向け】 「このたびはご改築、誠におめでとうございます。新たな環境におかれましても、ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。ささやかではございますが、心ばかりの品をお贈りいたします。」
このように、相手に合わせて言葉を選ぶことで、より心に響くメッセージになります。決して難しく考えすぎる必要はありませんが、基本的なマナーを守りつつ、あなたなりの思いを丁寧に表現することが大切です。
リフォーム祝いのお返しはどうすればいい?
リフォーム祝いに対してお返しをするべきかどうかは、相手との関係や地域の慣習によっても変わってきます。ただし、相手が高額な品物や現金を贈ってくれた場合には、基本的には何らかの形で感謝の気持ちを示すのが丁寧な対応です。
まず、お返しを「必ずすべき」という決まりはありません。しかし、新築祝いと同様、リフォームに関するお祝いも「内祝い」としてお返しを贈ることがあります。
とくに目上の人や親族など、きちんとしたやり取りが求められる関係の場合は、お礼の品を用意しておくと安心です。
一般的に、お返しの相場はいただいたお祝いの金額の3分の1から半額程度が目安とされています。たとえば、1万円をいただいた場合には、3,000円〜5,000円程度のお返しをするのが妥当です。
ただし、あまりにも高価なお返しをすると相手に気を遣わせてしまうこともあるため、内容よりも「感謝の気持ちが伝わるか」に重きを置くことが大切です。
お返しに選ばれる定番の品物には、お菓子、タオルセット、グルメギフトなどがあります。特に「消えもの」と呼ばれる、使えばなくなる消耗品は、相手に負担を感じさせにくく、気軽に受け取ってもらえるためおすすめです。
地域によってはお米やお茶などの品も喜ばれることがあります。
お返しを贈る際には、のし紙をつけるのがマナーです。表書きには「内祝」と記し、紅白の蝶結びの水引を使用します。名前は基本的に受け取った側(贈り主)個人の名前で書きますが、家族全体で贈る場合には世帯主の名前を書くのが一般的です。
渡すタイミングは、お祝いを受け取ってから1ヶ月以内を目安にするとよいでしょう。遅れすぎると気持ちが伝わりづらくなるため、なるべく早めに手配することをおすすめします。
また、直接手渡しが難しい場合には、配送にメッセージカードを添えることで丁寧な印象を与えることができます。
このように、リフォーム祝いのお返しは形式よりも「気持ちを形にすること」が大切です。贈ってもらった好意に対して誠意ある行動を取ることで、良好な人間関係を保つことができます。
相手との今後のお付き合いを見据え、過不足のない、心温まるお返しを心がけましょう。
お菓子はお祝いギフトとしてアリ?ナシ?
お菓子は、リフォームや改築祝いのギフトとして「アリかナシか」と迷う人も少なくありませんが、基本的には「アリ」といえます。
ただし、どんなお菓子を選ぶか、誰に贈るのか、どんな場面で渡すのかによって、ふさわしいかどうかが変わってきます。見た目や価格だけで選ぶのではなく、いくつかのポイントを押さえたうえで選ぶことが大切です。
まず、お菓子の最大のメリットは「受け取りやすさ」です。現金や商品券だと重く感じる人もいますし、インテリア雑貨などは好みに合わない可能性がありますが、お菓子であれば多くの人が気軽に受け取ることができます。
特に、相手がご家族と同居している場合は、みんなで分けて食べられるので実用的です。
また、消えもの(=食べてなくなるもの)は、もらう側にとって負担になりにくく、お返しを気にせず済むことが多いという点も好まれる理由です。
とくに「内祝いまでは考えていないけれど、軽くお祝いの気持ちを伝えたい」といった場面では、お菓子がちょうどいい選択肢になります。
一方で注意したいのは、お菓子の「選び方」です。スーパーで手に入るような普段使いのお菓子では、祝いの場にはふさわしくありません。
リフォーム祝いとして贈る場合は、見た目にも華やかで高級感のあるスイーツや、個包装された焼き菓子・和菓子などを選ぶとよいでしょう。賞味期限が短すぎるものや、冷蔵保存が必要な商品は避けたほうが無難です。
さらに、のしや包装も重要なポイントです。お菓子を贈る際も、簡単なラッピングではなく、慶事用ののし紙を付けることで正式なお祝いとしての体裁が整います。
表書きには「御祝」「祝御改築」などと記載し、紅白の蝶結びの水引を使用するのが基本です。これにより、単なる手土産とは異なる「お祝い」としての意味合いが伝わります。
ただし、相手にアレルギーがある場合や、食生活に制限がある方には配慮が必要です。心配な場合は、お菓子を直接贈るのではなく、スイーツのカタログギフトなどで選んでもらう方法もあります。
このように考えると、お菓子はリフォーム祝いとして十分にふさわしい贈り物の一つです。適切な選び方と贈り方を意識すれば、気軽でありながら心のこもったギフトとして、相手に喜んでもらえるでしょう。
場の空気を和ませるような、やさしいお祝いの形としておすすめです。
リフォームのお祝いで失敗しないための総まとめ
- リフォームのお祝いは現金・商品券・実用品が定番
- 現金に抵抗がある場合はカタログギフトが無難
- 花を贈る際は色や種類に注意が必要
- 贈り物は相手のライフスタイルに合ったものを選ぶ
- 火や災害を連想させるモチーフは避ける
- 小規模なリフォームにはご祝儀不要なケースもある
- ご祝儀は奇数の金額を包むのが縁起がよい
- ご祝儀袋は紅白の蝶結びとし、表書きは「御祝」などを使用
- リフォーム内容によって「改築御祝」や「改装御祝」と表記を変える
- お祝いの相場は家族なら1万〜3万円、友人は5千〜1万円程度
- 親に贈る場合は金額より気持ちを重視する
- 贈り物のラッピングは包装紙や紙袋まで気を配る
- メッセージは忌み言葉を避け、手書きだとより丁寧
- お祝いのお返しは3分の1〜半額程度が目安
- お菓子は消えもので気軽に贈れるお祝いギフトとして好まれる